
100年前の超高層ビル建設から今こそ学びたい真理
予算と工期を守り、しっかりと便益を出すビッグプロジェクトは全体のわずか0.5%。
一方、お手本ケースがアメリカ・ニューヨーク市マンハッタン区にそびえたつ世界最高峰の超高層ビル「エンパイヤ・ステート・ビル」。102階建てで最頂部は443m。100年前に当初予定通りの建設期間18か月で完成し、総工費も予算を下回った。
その違いを生んだ要因はどこにあるのか。
『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』より、「先例」に学ぶ重要性をお届けする。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
著者:ベント・フリウビヤ
オックスフォード大学教授。世界中の兆円規模のメガプロジェクトを研究、1万件以上の成否データを保有する唯一無二の存在。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
モノに眠った「経験」を利用する
ドイツの哲学者フリードリヒ・フォン・シェリングは、建築を「凍れる音楽」と言い表した。この美しく記憶に残るフレーズを、私はこう言い換えたい。技術は「凍れる経験」である、と。
プロジェクトの計画者は、ほかの条件が同じなら、「経験豊富な技術」を選ぶべきだ。その理由は、住宅メーカーが経験豊富な大工を選ぶべき理由と同じである。
このとらえ方は一般的ではなく、むしろ技術は新しければ新しいほどよいと考えられている。そのうえカスタム設計も、「ユニーク」「画期的」「独自」などと称賛される。
経験を正しく評価する意思決定者は、新しい技術を警戒するはずだ。なぜなら、新しい技術とは「経験不足の技術」なのだから。また真に「唯一無二」のものには警鐘を鳴らさなくてはならない。
それなのに、「新しい」や「ユニーク」は避けるべき特徴どころか、セールスポイントとみなされることが多い。これは大間違いだ。計画立案者と意思決定者はたびたびこの間違いを犯す。プロジェクトが期待外れに終わる主な理由は、ここにある。

「反復」が上達をもたらす
ビッグ・オウ(巨大債務)の対局にあるのが、エンパイア・ステート・ビルだ。
エンパイア・ステート・ビルは100年前に18か月という驚異的な速さで建てられた。(建設の経緯など詳しくは『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』で解説しています)
この功績は、工事を円滑、迅速に進めるために綿密な検証を重ねて計画を立てた、建築家のウィリアム・ラムの手腕によるところが大きい。
だがもう1つの要因として、ラムが「革新的手法の不確実性を回避するために」、実績のある既成技術にこだわったことが挙げられる。たとえば、「手作業」を可能な限り避け、「完璧な精度で大量に複製できるように」設計されたパーツを「現場に運んで、組立ラインの自動車のように組み立てた」。
またパーツの種類と複雑性を最小限に抑え、各階の設計も可能な限り同一にした。おかげで作業員は同じ作業の反復を通じて学習することができた。つまり、作業員は102階建てのビルを1個建設したのではなく、1階建てのビルを102個建設したのだ。プロジェクト全体が学習曲線を駆け上がり、ペースは加速の一途をたどった。
とはいえ、この計画も、初心者の手にゆだねられていたら失敗したかもしれない。だが施工を担当したゼネコンは、「高層ビルの効率的、迅速な建設の実績が豊富な」スターレット・ブラザーズ・アンド・イーケンだったと、歴史家のキャロル・ウィリスは書いている。
ラムがこの種のビルの設計をすでに経験していたことも幸いした。ノースカロライナ州ウィンストン・セーラムの、かつてR・J・レイノルズ・タバコ・カンパニーの本社だったレイノルズ・ビルディングは、エンパイア・ステート・ビルを小さく短くしたような、アールデコ様式の優美な建物である。
ラムが1927年に設計したこのビルは、エンパイア・ステート・ビルの建設が始まる1年前の1929年にオープンし、同年にアメリカ建築家協会の年間建築賞を受賞した。ラムは過去の成功例という、建築家が望み得る最高の経験を、エンパイア・ステート・ビルの設計、建築に活かすことができたのだ。
では、エンパイア・ステート・ビルは、過去の設計を活用したり、意図的に単純で反復的な設計にしたことによって、価値がおとしめられただろうか?
とてもそうは思えない。エンパイア・ステート・ビルは時代を象徴する建物になり、「世界一高いビル」という垂涎(すいぜん)の称号までを(不要なリスクを負わずに)勝ち取った。
すべての大型プロジェクトが、このような成功をめざすべきだ。その可能性を大幅に高めるための優れた方法こそが、経験を最大限に活用することである。
「熟練した直感」は正しいことが多い
だが、プロジェクトを成功させるためには、「凍れる」経験が欠かせないのと同様、「凍れぬ」経験、つまり形にならない、人々の生きた経験を活用することも大切だ。
プロジェクトリーダーをずば抜けた存在にしているのが、まさに彼らの生きた経験である。そしてプロジェクトの計画立案と実行においては、経験豊富なチームを率いる経験豊富なリーダーに勝る資産はない。
なぜ経験は仕事の質を高めるのだろう? 誰かにそう訊いたら、おそらく「経験者は知識があるから」のような答えが返ってくるだろう。そのこと自体は間違いではない。たとえば道具を使う人はその経験を通して、「使用前にセーフティロックを外す」などの知識を得る。
だがそうした知識は、別に経験しなくても、誰かに聞いたりマニュアルを読んだりすれば手に入る。この種の知識は「形式知」と呼ばれる。しかし科学者で哲学者のマイケル・ポランニーが示したように、人間が所有し利用できる最も有用な知識の多くは、形式知ではなく、「暗黙知」である。
暗黙知とは「感じとる知識」だ。何かを言葉で説明しようとしても、完全に言葉に置き換えることはできない。ポランニーの言うように、「人は語れる以上のことを知っている」のだから。
大人が子どもに自転車の乗り方を完璧に指示したつもりでも(「片足をペダルにつけて踏み込んだら、もう片方の足で反対側のペダルを踏んで」など)、子どもは最初のトライで必ず失敗する。なぜなら、指示が完璧ではないからだ。
だいいち、完璧な指示など与えられるはずがない。大人が自転車の乗り方について知っていることの大部分は(これくらいの速度で曲がるときはこうやってバランスを取る、など)、「感じとる」知識だ。どんなに言葉を尽くしても、完全には言葉に置き換えられない。だから、どんなに役に立つ指示があったとしても、自転車の乗り方を学ぶには、試行錯誤をくり返すしかない。経験を積み、自分で暗黙知を生み出すということだ。
これは自転車乗りやゴルフのような身体的活動では常識だが、その他の多くのことにも当てはまる。ポランニーが暗黙知の概念を生み出したのも、科学者がどうやって科学を探究するのかを研究していたときだった。
経験値の高いプロジェクトリーダーは、自分が運営するプロジェクトのさまざまな側面の暗黙知を持っている。暗黙知は判断力を大いに高める。なぜなのかを言葉で説明できなくても、何かがおかしいと感じたり、もっといい方法があるような気がしたりすることは多い。
多くの研究が示すように、専門家の直感は、適切な条件下では非常に信頼性が高い。また驚くほど正確なこともある。美術専門家たちが、古代ギリシアのものとされる彫像を見た瞬間に贋作(がんさく)だと見抜いたという、有名な話がある。彫像は科学的鑑定に合格していたし、専門家自身もなぜおかしいと感じたのかを言葉にできなかったのに、だ。
これはありふれた、ただの勘ではなく、「熟練した直感」であり、専門領域で経験を積んだ本物の専門家だけが持てる、強力なツールである。

<本稿は『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』(サンマーク出版)から一部抜粋して再構成したものです>
(編集:サンマーク出版 Sunmark Web編集部)
Photo by Shutterstock
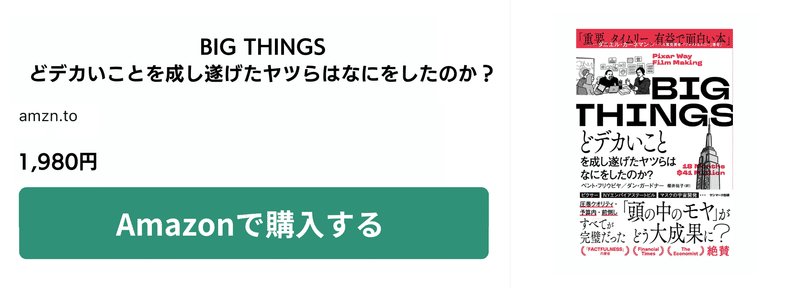
◎関連記事

