
「遣唐使」「元寇」に通じる日本のずっと変わらない地政学的力学
歴史は繰り返すと言いますが、それは「地理」が変わらないから――。
日本の対外関係を理解する鍵は、日本列島と朝鮮半島という揺るぎない地理にあります。古代から現代まで、この地政学的な配置が日本の進路を決定づけてきたのです。
地政学動画で平均150万回再生を記録する社會部部長が、不変の地政学の法則を解説した『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』よりお届けします。
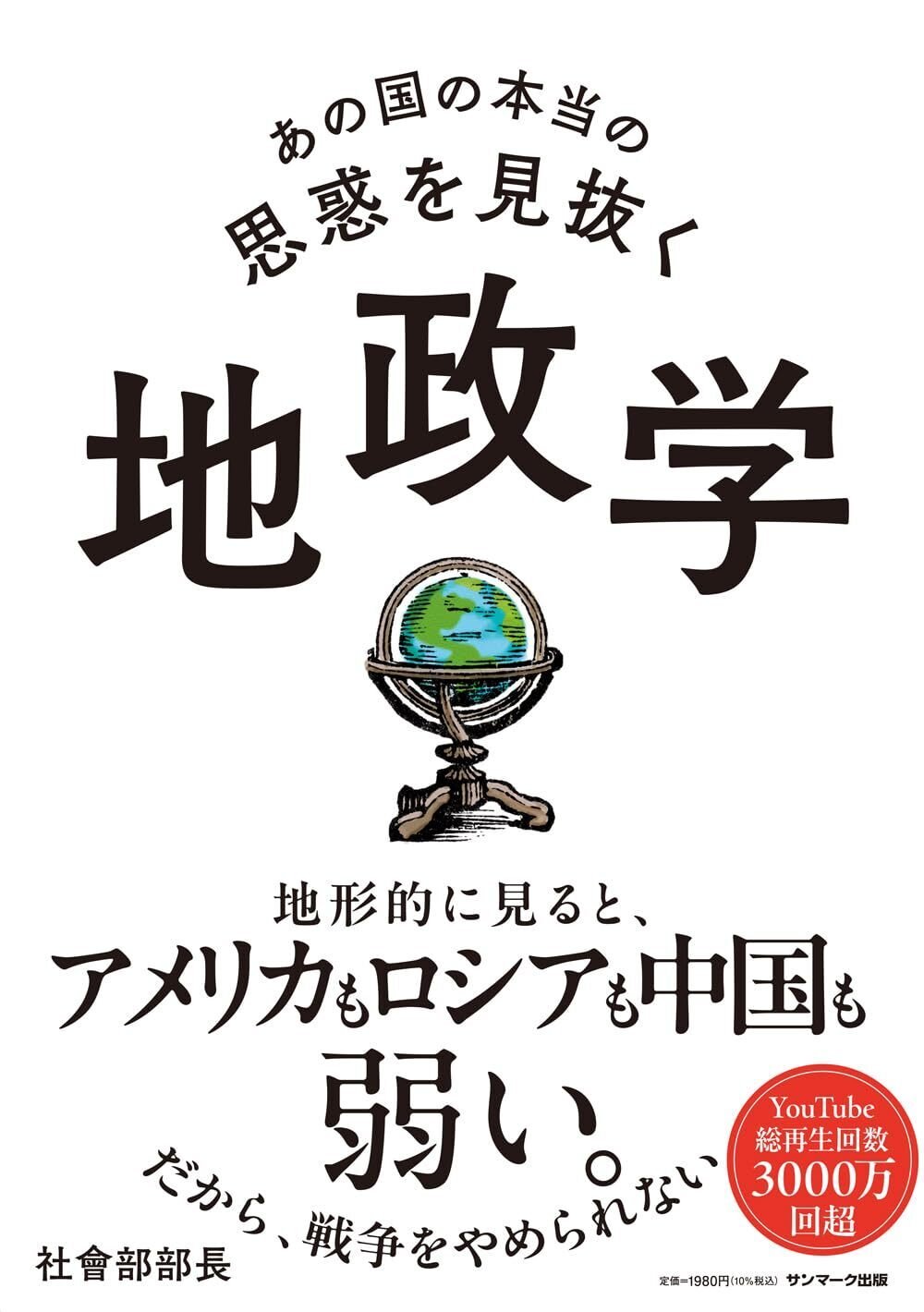
日本/大陸国家になろうとした海洋国家
世界地図の上に描かれる日本を遠目で見ると、あらためて当たり前の事実に気がつきます。それは、北で大陸に近接し、南で広い海洋に面することです。
もう1つ気づくのは、朝鮮半島が橋のようにユーラシア大陸から伸びて、九州と至近距離に達していることです。地図の上に指を置いて朝鮮半島を隠してみると、意外とここが大きく、もしなかったら日本が大陸からかなり離れることがわかります。
日本は海に囲まれた地形も幸いして、世界史上稀(まれ)に見るほど外国と戦争をしなかった歴史を持ちます。しかし、そんな日本でも対外戦争が全くなかったわけではありませんでした。日本はユーラシア大陸から海で隔てられていたとはいえ、朝鮮半島で半ば繫がっている、絶妙な距離に浮かんでいたからです。
日本と大陸の交流をほぼ必ず媒介してきたのが、朝鮮半島です。朝鮮半島は、日本と大陸を結ぶ「橋」のような場所で、ここを通って大陸の文化や知識、技術などが日本に伝わってきました。
戦争も例外ではありません。日本にとって、朝鮮半島は大陸勢力が日本を攻める通り道、または日本が大陸を攻める通り道として使われました。日本を「城」とすると、日本海が「水堀」の役割を果たし、朝鮮半島は城へと続く「橋」のようなものでした。
このため、日本にとって今も昔も最も重要な地政学的課題は、朝鮮半島を守ることなのです。言い換えれば、大陸勢力に対する日本の防衛線は、朝鮮半島と日本海の二重となっており、日本は可能な限り大陸勢力の進軍を朝鮮半島で堰き止め、それが突破されれば九州で上陸を防ぐことを目指してきました。
日本が関わった対外戦争の多くにはこの地政学的力学が根底にありました。代表的なものだけでも、白村江の戦い、元寇、朝鮮出兵、日清・日露戦争、日中戦争、朝鮮戦争。また、現代の北朝鮮問題にもこの力学が少なからず働いています。
日本史を地理的視点で振り返ると、意外にもそこには法則性があることに気がつきます。7世紀の白村江の戦いと今の北朝鮮問題の類似点、13世紀の元寇と日露戦争の類似点、16世紀の朝鮮出兵と第二次世界大戦の類似点などが示すように、日本の戦争は歴史を通して地理によって導かれてきました。それでは、朝鮮半島と日本の地政学的歴史を、白村江の戦いから見ていきましょう。
朝鮮半島という橋
日本が初めて経験した対外戦争「白村江の戦い」
日本と朝鮮半島の地政学的関係が最初に表面化したのは、663年に起きた白村江の戦いでした。あまり聞き馴染みのないこの戦争ですが、これは日本が経験した最初の大規模な対外戦争として重要な意義がありました。
この戦いは一言でいえば、「唐の日本侵略を防ぐための戦争」でした。4世紀から7世紀にかけて、朝鮮半島には高句麗(こうくり)、新羅(しらぎ)、百済(くだら)の3つの国があり、半島の中で『三国志』さながらの長い争いを繰り広げていました。そしてこの中で日本と仲が良かったのが百済でした。
ところが、この3つの国々が争っているうちに、唐が新羅と組み、百済を攻めて滅ぼしてしまいました。しかし、それでも百済の王は国の復活を目指し、日本に救援を頼んできました。
日本にとって、百済の要請に応えるかどうかは難しい問題でした。百済は朝鮮半島の一番南に位置する、日本にとっての緩衝国であり、百済を助ければ唐の南進を防げます。ただ、助けに行った結果もし負けてしまったら、その勢いで唐に攻められる日が早まるかもしれません。つまり、負けるくらいならば唐と敵対しない方が良いかもしれなかったのです。
それでも、日本は最終的に百済を助けることを決め、大規模な軍勢を朝鮮半島に送りました。この結果起こったのが、白村江の戦いです。しかし、日本と百済の連合軍は、最初はやや優勢だったものの、唐と新羅の強力な軍隊に徐々に押され、最終的には敗北しました。
百済が滅んだ上に唐と敵対するという、最悪の結果になってしまい、日本は唐の侵略を恐れるようになりました。そこで日本はすぐに唐軍の上陸に備え、九州の海沿いに防壁を築いて、多数の兵士(防人(さきもり))をここに配置しました。また、対馬との連絡も常に行って、戦争の兆候をいち早く察知できるようにしました。こうして日本は、唐がいつ攻めてきても良いように備えたのです。
ところが、しばらくして唐と新羅が対立するようになったため、唐は日本への関心を失いました。むしろ唐は新羅と日本が協力しないよう、遣唐使をすぐに再開するなど、日本との平和的な関係を重視しました。ちなみに、新羅と日本の関係が悪化したことにより、白村江の戦い以降は、遣唐使は航路を変更せざるを得なくなりました。
当初、遣唐使は北路という、友好国・百済の沿岸を行く航路を使っていました。しかし、新羅が朝鮮半島を制したことにより半島の沿岸は通れなくなったため、遣唐使は東シナ海を横断する南路を行くしかなくなりました。学校では「遣唐使の多くが中国に辿り着く前に死んだ」という衝撃的な歴史を習いますが、これは白村江の戦いにより、わざわざ波が荒く、陸地がない東シナ海に航路を移した結果でした。
このように、朝鮮半島の国々は中国の南進を止める防波堤のような役割を果たしました。最初は百済が単独で戦い、一度滅ぼされれば日本が応援し、それも失敗すると九州で防御の準備、しまいには新羅が新たな防波堤となりました。このように日本は朝鮮という、日本を脅かすほど強くはなく、中国にすぐ負けるほど弱くもない国が半島にあったおかげで、歴史上何度も救われてきたのです。これは次の対外戦争である元寇でも同じでした。

日本史上最大の危機「元寇」
元寇は、日本史上最大の危機といっても過言ではない出来事です。その理由は、これが大陸勢力が朝鮮半島の南端に到達した史上唯一の出来事であり、朝鮮という防波堤が突破されて敵軍が日本に渡ってきた唯一の戦争でもあるからです。
モンゴル帝国は当初日本に野心的ではなく、むしろかなり丁寧に接しながら友好関係を築こうとしました。なぜモンゴル帝国が日本に接近したかといえば、中国の南宋という国を征服するために、日本の協力が欲しかったからです。南宋は軍事力が強く、ユーラシア大陸を席巻していたモンゴル帝国でも苦戦していました。
そこでモンゴル帝国は、日本を南宋包囲網の一員に引き入れたかったのです。しかし、日本は度重なるモンゴル帝国からの要請をすべて無視しました。なぜ強大なモンゴル帝国をそれほど無視したかといえば、当時の鎌倉幕府の外交に関する情報はすべて南宋から入ってきており、南宋は日本がモンゴル帝国に協力しないよう助言し続けたからです。
痺れを切らしたモンゴル帝国は、1274年に高麗(朝鮮)と共に約900隻の船と2万人以上の兵士で日本を攻めることを決めました。九州に上陸したモンゴル軍は日本軍を圧倒しましたが、日本は奮戦し、なんとか撃退することに成功しました。
モンゴル帝国は一度の敗北では諦めず、日本にもう一度攻め込もうと準備を始めます。日本もこの2度目の戦いに備え、九州に全長20㎞、高さ2mの防壁を築きました。そして、1281年、モンゴル軍は、今度は船を約4000隻、兵士を14万人と、戦力を大幅に増やして日本に攻め込みました。しかし、日本側は強化した守備と神風のおかげで、再び侵略を防ぐことができました。ちなみに、このときのモンゴル軍があまりにも残虐だったため、「モンゴル」が「むごい」という言葉に転じたといわれています。
元寇で日本が生き残った理由には、日本軍の戦術や神風が注目されがちです。ただ、やはりここでも朝鮮の役割は無視できません。朝鮮(高麗)は、元寇の前に約30年間、モンゴル帝国に抵抗しました。結果的に降伏したとはいえ、この期間に日本はモンゴル軍の戦い方を伝え聞き、撃退体制を整える時間的余裕を得ました。朝鮮半島はまさに、日本の緩衝地帯として機能したのです。

<続きは後日公開、次回は豊臣秀吉の朝鮮出兵を解説します、本稿は『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』(サンマーク出版)から一部抜粋して再構成したものです>
(編集:サンマーク出版 SUNMARK WEB編集部)
Photo by shutterstock
サンマーク出版の公式LINE『本とTREE』にご登録いただくと、この本『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』の実際と同じレイアウトで目次を含み「プロローグ」「序章 今、地政学を学ぶ意義」まで冒頭40ページをすべてお読みいただけます。ご登録は無料です。ぜひこの機会に試し読みをお楽しみください!

【著者】
社會部部長(しゃかいぶぶちょう)
YouTubeチャンネル「社會部部長」。一切の素性を隠したままわずか30本ほどの動画で33万人登録、3000万回再生を達成した今最も注目される歴史・地政学解説チャンネル。
https://www.youtube.com/@shakaibubucho


