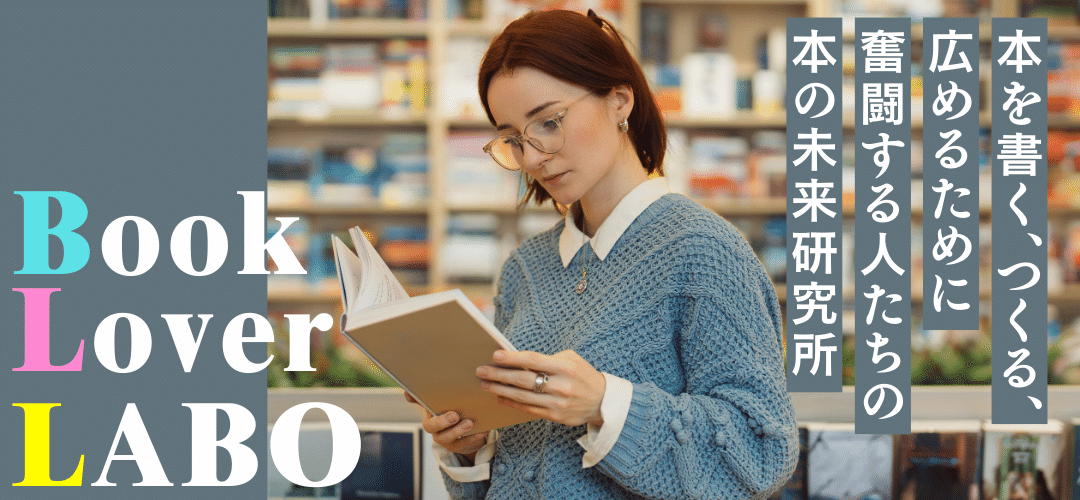世界の仕組みを知りたい人に『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』を読んでほしい理由
調達コンサルタントとして活動し、テレビ、ラジオなど数々の番組に出演、企業での講演も行っている坂口孝則さんはさまざまなジャンルにまたがって毎月30冊以上の本を読む読書家。その坂口さんによる『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』(著:社會部部長、サンマーク出版)のブックレビューをお届けします。

アメリカ・ファーストへの的外れな批判
「アメリカ・ファーストって本当に問題なのか?」
今年1月に、アメリカでドナルド・トランプ新大統領が就任してからというもの、日本の知識人層はいっせいにトランプ大統領を批判している。そのなかでもやり玉に挙がっている話題が、貿易交渉や外交政策においてアメリカの経済的利益や安全保障を最優先する「アメリカ・ファースト」政策だ。世界のことを考えない自国優先主義を指向するトランプ大統領をこき下ろす風潮が目立つ。
しかし、その主張は的を射ているのだろうか。逆に自国を最優先しない政治家とは誰なのか。日本ではアメリカのほうばかりを向いている政治家が批判され続けてきたように思う。であれば日本もジャパン・ファーストで考えるのが当然ではないだろうか。もっといえば、日本の政治家がもっとアメリカの政治家を見習って、自国益を他国からひっぱってきてもらいたいと考えている日本国民は多いのではないだろうか。
名著『大国政治の悲劇』(ジョン・J・ミアシャイマー著)が述べる通り、各国のなかでは警察権力がいるものの、国家間では取り締まる警察がいない。国連も完全には機能しない。それはウクライナとロシアの戦争を見てもあきらかだ。
17世紀の政治哲学者トーマス・ホッブスが指摘したように、支配者のいない自然状態では人々は常に争いの危険にさらされる。それと同様に、現代の国際社会においても、国家と国家は常に対立や闘争の可能性を抱えており、強者か戦略あるものが生き残る弱肉強食の現実がある。
私たちはこの混迷する時代に生きて、何を指針にすればいいのか。
『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』は何が面白いか
そんな観点で『あの国の本当の思惑を見抜く 地政学』を読むと面白い。私はビジネスパーソンとして、サプライチェーンに関わっている。サプライチェーンとは、企業が必要とする部材や材料、サービスなどを世界各国から買い集める仕事だ。地政学の知識は平和な時代には考慮する必要がないものの、緊張が高まる時代には必須だ。サプライチェーン領域のコンサルティングに従事している私にとって、現場の実務に役立つ1冊とも言える。
本書の前半部分は、海に囲まれた国家と、陸続きの国家の特徴が語られる。海に囲まれた国家は攻撃されにくい。あるいは、スイスのように山岳に囲まれた国家は攻撃を受けにくい。このような物理的な説明がなされる。海洋国家と大陸国家。いわゆる、シーパワーとランドパワーの議論だ。
陸続きの国家は、隣国からいつ攻め入られるかわからないから強い陸軍を持たねばならない。海洋国家の代表であるアメリカは、だからこそ大陸国家に協力してきた。
イギリスやアメリカのような海洋国家の強さを真に支えるのは「強い海軍」ではなく、「強い陸軍を必要としない環境」なのです。
ハッとする一文だ。アメリカはだからこそ予算を投じて、陸軍に依存しない仕組みで強靭化を図ってきたのだ。そもそもアメリカの強さははかなく、きわめてもろい砂の城のうえに立っていると著者は指摘する。

実証による国家の行動理由のクリアな分析
本書が面白いのは、どこまでも現実的かつ過去の実証に基づいている点だ。世界の政治のダイナミズムは、どこか一つだけの国が強くなりすぎるのを嫌う歴史が繰り返されてきた。
本書の分析が明瞭なのは、次のような記述だ。
アメリカはただ「中国は独裁国家だから」とか「人権侵害をしているから」「経済的に競争関係にあるから」といった理由で対抗しているのではありません。アメリカが対抗する理由は、中国がユーラシア大陸を制覇しかねないほど強い潜在覇権国だからです。アメリカを根底で動かしているのは、「大陸の勢力均衡を保たなければ生存できない」という防衛本能なのです。
これほど端的な説明があっただろうか。
<編集部註:潜在覇権国とは「将来的にすべての国を支配する勢力を持つ覇権国になるかもしれないほど強い国」のことです>
この「大陸の勢力均衡を保たなければ生存できない」というロジックを使って、本書ではロシアがなぜ領土を拡大し続けなければならない宿命に陥っているのか。また中国が遊牧民との闘いを経て海洋進出を行っているかをクリアに説明している。本書の特徴は、国家の地理的な特徴をもとに大きな行動方針を明らかにしたところにある。
ちなみに、歴史ファンには小さな雑学の宝庫ともいえる。ペリーの黒船よりも、ロシアからの開国要求が日本の開国に影響を与えた理由が述べられ、面白い。たとえば次のようなものだ。
北からの脅威に対抗するため、江戸幕府は北海道の統治を強化する方針をとり、何度も探索隊を派遣しました。あの有名な伊能忠敬の『大日本沿海輿地全図』もこの一環です。

「真珠の首飾り」の航路が意味すること
本書のテーマはタイトルにあるとおりの「地政学」だ。たとえば某国が地政学的なリスクを踏まえて、特定製品の輸入元をA国からB国に切り替えたとする。そうなればB国の経済が活性化して、B国における関連企業の株式に“賭ける”ことが利益をもたらすだろう。
私が本書を読んでいたときに、「なるほど!」と叫んだ箇所がある。
「中国がマラッカ海峡を恐れている」という趣旨の記述がある。中国は10億人を超える民を“食べさせなければ”ならない。マラッカ海峡はマレーシアやシンガポールを通る海道だ。世界地図を眺めてほしい。アメリカ寄りとみられるそれらの国からそっぽを向かれると中国は危機に陥る。
だから、マラッカ海峡ではなく、中国からミャンマーを通り、マラッカ海峡をぬけるルートを開発したとある。本書ではこれを「真珠の首飾り」と表現している。世界地図がないと説明が難しいのだが、中国から、ミャンマーをとおり、インドをぬけ、さらにパキスタン方面にいたる航路が首飾りのように見えるのだ。
地政学はビジネスに役に立つ
ここで私の個人的な話をお許しいただきたい。私はコロナ禍前、さらに2021年2月の軍事クーデターでミャンマーに軍政が始まる前に、何度かミャンマーに出張で出向いた。その際に、ミャンマー人の優しさに触れて感銘を受けた。ただ、同時にミャンマーの経済発展と、アンダマン海に抜けるルートの成長度合いに驚いた。
というのも、中国から次々にトラックがやってきて荷物をおろし、その荷物を積んではミャンマーの港から船舶が次々と出発していく。アンダマン海に抜ける港町では、トラック運転手が休息する飲食店から、タイヤの整備工場、宿泊所などが乱立していた。私は残念ながら経験したことはないものの、日本の高度経済成長期はこんな感じだったのか、と思うくらいミャンマーという国は訪問するたびに成長していた。
しかし、本書を読んで思った。なるほど、地政学的に中国がミャンマーを経てアンダマン海に抜けるルートを開発する必然があったのだ。その必然に乗っかればいい。だって物流は経済の血液だから、その近辺の土地を買っておけば値上がりを待つだけだ。
地政学は役に立つ。それは教養の意味だけではない。実利につながる。
なるほど。私は本書を読みながら、軍事産業のファンド(投資信託)でも買おうかと考えていた。もちろん、こんな単純な思考が地政学的思考には程遠いと知りながら。
(編集:サンマーク出版 SUNMARK WEB編集部)
Photo by shutterstock
坂口孝則/調達コンサルタント
大学卒業後、メーカーの調達部門に配属される。調達・購買、原価企画を担当。バイヤーとして担当したのは200社以上。コスト削減、原価、仕入れ等の専門家としてテレビ、ラジオ等でも活躍。企業での講演も行う。
サンマーク出版の公式LINE『本とTREE』にご登録いただくと今回ブックレビューをご紹介した『あの国の本当の思惑を見抜く地政学』の実際と同じレイアウトで目次を含み「プロローグ」「序章 今、地政学を学ぶ意義」まで冒頭40ページをすべてお読みいただけます。ご登録は無料です。ぜひこの機会に試し読みをお楽しみください!

公式LINEの試し読みページにジャンプします