
紀伊國屋書店“ビジネス書のカリスマ”百々典孝さんに『BIG THINGS』の魅力を聞いてみた
関西を代表する大型書店、「紀伊國屋書店梅田本店」で長年にわたってビジネス書のコーナーを担当している百々典孝(どど・のりたか)さん。
“ビジネス書のカリスマ”と呼ばれ、これまで膨大な量のビジネス書を手に取ってきた百々さんが注目するのが、『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』(ベント・フリウビヤ、ダン・ガードナー/著、櫻井祐子/訳、サンマーク出版/刊)だ。
百々さんは、『BIG THINGS』を現代人必読の名著であり、人生の指針にもなり得る――と絶賛する。いったい何が、百々さんの心を動かしたのだろうか。その魅力を存分に語っていただいた。
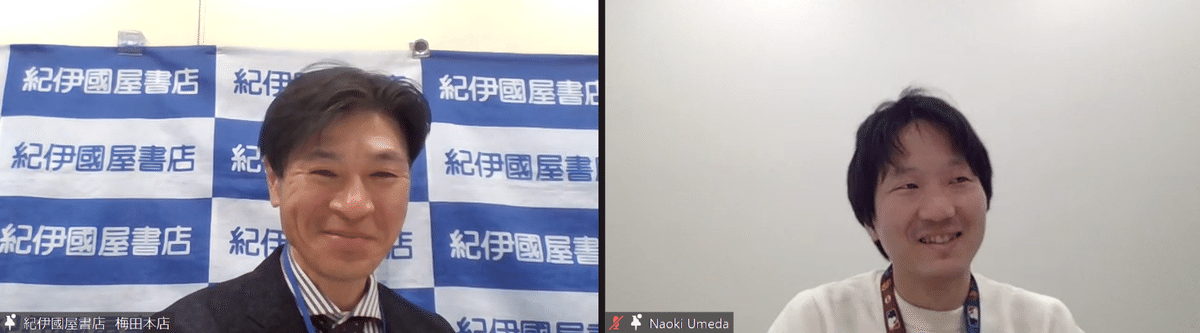
(右) サンマーク出版 統括編集長 梅田直希
『BIG THINGS』は学問として存在すべき名著
梅田:今回お会いする前に、僕が編集担当をした『BIG THINGS』の原稿をお送りしていたわけですが、正直なんて言われるか不安だったんです……
百々:え、そうなんですか?
梅田:ビジネス書の西のカリスマに、「面白くない」と言われたらどうしようって……でもお会いしていきなり「めちゃめちゃ面白かったですよ!」と言ってもらえたときは本当にうれしかった!
百々:あはははは
梅田:でも、もっと嬉しい言葉があって。「学問として存在してもいいレベル」「今、書店にないジャンルだけど、この本をきっかけに棚が誕生してほしい」この言葉を聞いたときは、感動しましたし、自信にもなりました! 改めて『BIG THINGS』を読んだ時の率直な感想を教えてください。

百々:まず、着眼点が新しいと思いましたね。過去に起こった戦争はたびたび研究されていますが、国家プロジェクトについて、成功か、失敗か、検証した本は読んだことがなかったのです。一件の国家プロジェクトが戦争に肩を並べるほど予算を消費することはままあります。その如何によって国が傾くことも珍しくないのに、なぜこれまで顧みられなかったのだろうと思いました。
梅田:国家プロジェクトには莫大な予算がつぎ込まれますが、是非が検証されることは、たしかにあまりない気がします。少なくとも、我々平民の耳に届かない、といいますか……
百々:そこから教訓を得られないのはとてももったいないですよね。ひとたびオリンピックのような国家プロジェクトを開催すると、国家予算の何%かがごっそり失われるわけでしょう。それこそ、過去の国家プロジェクトにかかった費用を積み重ねていったら、天文学的な金額になります。それでも、具体的な検証がほとんどなされていないんですよ。歴史に学び、過ちを繰り返さないためにも、『BIG THINGS』は必読の名著です。ビジネスパーソンにとっても、プロジェクトの大小を問わず、仕事に応用できるヒントが多い気がするんですよね。
梅田:そうなんです! すべての仕事は「plan → action」で成り立っていることを考えると、規模の大小関係なく、「予算内・期限内で最大便益」を成し遂げる方法は普遍的に誰しもが使える戦略であり、戦術だと思います!
百々:そうですね。個々のプロジェクトについて丁寧に書かれ、プロジェクトリーダーの気持ちが代弁されています。それこそ、仕事でプロジェクトリーダーを任された人や、コンサルタントになりたての人は手にとるべきでしょう。当店でもしっかり一般読者に向けて発信していきたいと考えていますし、これをきっかけに親棚が誕生して欲しいと思うほどの名著だと思います。
梅田:読むと、今後取り組むすべてのビジネスに良い影響が出る本だと思っていて、しっかりとした分析の結果、導き出された戦略がシンプルで覚えやすいんですよね。
百々:「ゆっくり考え、すばやく動く」ですよね! 今、幅広い層に売れている本の一つが、『世界は経営でできている』(岩尾俊兵/著、講談社現代新書)という新書です。人生を一つのプロジェクトとして捉えるという斬新な発想の本なのですが、『BIG THINGS』を併せて読むと、人生の指針を考えるきっかけができると思いますよ。

国家プロジェクトの見方が一変する
百々:この本を読むと、様々なプロジェクトの見方が変わると思います。
梅田:たしかに、世界を見る目も変わるかも。
百々:先日、紀伊半島にある串本町に、民間ロケットの発射現場を見に行きました。行政や民間企業も応援していたし、警察官が動員され、交通規制も行われ、厳重に防衛線を張っていました。しかし、海上封鎖ができず、海上約6.5kmの位置に船が残っていたせいでロケットを発射できずに終わってしまいました。こうした失敗は『BIG THINGS』を読むと十分に起こり得る事態だとも思いましたし、未然に回避できたとも感じました。いくらでも準備はできたと思うので、とても残念でしたね。
梅田:本書で導き出されるのは、大きなプロジェクトを成功させるコツは「ゆっくり考え、素早く動く」という言葉に集約されるということ。昨今のプロジェクトを見ると、真逆になっているケースが多いですね。「とにかくまず行動。走りながら考えよう」みたいな……
百々:はっきり言って、『BIG THINGS』は基礎教養になって欲しいと思うほど内容が充実した本だと思います。職業、年齢、性別を問わず、広く読まれるべき一冊ですね。私は、人間にとってもっとも重要なものは好奇心だと思うんです。好奇心の扉がいっぱいある人間は面白い。そして、この本は好奇心の扉を開けてくれる一冊だと思います。
梅田:世界の見え方が変わって、ビジネスに詳しくなるだけでなく、「もっと知りたい」と思わせてくれる本かも。
百々:読み手の好奇心を刺激するのは本の役割ですし、そういった本が増えてくれば、出版業界もますます面白くなると思いますね。

出版社や書店の未来について感じること
梅田:出版業界の話でいえば、長年に渡って売り場を作ってきた百々さんの目線から、昨今の出版社に対して思うことはありますか。
百々:出版社には、100年先に残るような本を覚悟して出して欲しいですね。来年度決算のことを考えて出すのだけはやめて欲しい(笑)。そういう本は、表紙のデザインにもお金がかかっていなかったりしますから、パッと見ただけでわかりますよ。自信がないからこそ、コストをかけられないのです。
梅田:確かに、そういった本は多いかも、です…(自戒もこめて)
百々:もちろん出版社には出版点数のノルマがあることは理解できます。しかし、それが行き過ぎると、他社でヒットした本と同じテーマで本を作る例が増えてしまいます。そういう本を手に取ったお客さんがいたとしましょう。読んで何かためになったらいいのですが、内容がいまいちだと、本が嫌いになってしまう可能性がある。出版点数が増えることで市場が活性化するかもしれませんが、間違っても、読者人口を減らすことに繋がってはいけないと思います。
梅田:つまらない本を出すことで、読者人口を減らすかもしれない……本を読む人の減少が叫ばれてひさしいですが、これは我々「作り手」の問題ですね。肝に銘じます。
百々:ぜひお願いします! 一方で、書店の減少が問題視されていますが、人口も減少していますし、減っていくのは仕方ないと思うんです。ただし、出版社が過去と同じ本ばかり作っていたら、落ちていくのは当たり前です。本は生活の中で必要性に迫られたり、より高い水準の生活をしたいとか、基礎教養を高めたいとか、具体的な理由があるときに読まれるもの。人々が心から欲するような、知的好奇心を刺激する本を作る努力はすべきでしょうね。
梅田:個人的には、翻訳書をよく手がけることもあるのですが、SNSでファンが多かったり、すでに著名でファンが大勢いたりする方の本は作らないようにしているんです。僕があまのじゃくで「みんなが右むくなら左!」という性格によるところも大きいのですが、ファンを獲得するまでのご本人の努力や、それまで支えてくれていた方の尽力を利用しているような気がして、スッキリしないんですよね。
百々:出版社は、話題性を高め、初動で大きな部数を売れば正解、という売り方をやめるべきでしょう。30~50年前で出た本が地方都市でロングスパンで売れているとか、そういう本も大事なんじゃないかな。出版社はビッグヒットを狙うのもいいけれど、これからは長く続く本に注力すべきだし、書店も文化を発信する拠点として生き残っていく方法を探るべきでしょうね。
梅田:百々さんが理想とする書店像は、出版社員の立場からも気になるところです。
百々:「行けば何か面白いものがありそうだ」という動機で人々が集まり、本を読んで好奇心の扉が開き、社会の仕組みについて理解が深まっていく。こういった好循環が生まれるのが、私の理想の書店です。「お祭りが行われている神社」みたいなイメージでしょうか。
梅田:なるほど! たしかに、これだけ目的意識が違う人が一同に集まる空間も珍しいですよね。洋服屋さんに行く人は「服が欲しい」と思っているわけだし、レストランにいる人は「お腹空いた」からそこにいる。けど、書店にいる人は、「勉強したい」「面白いものが読みたい」「悩みを解決したい」など、いろんな気持ちの人がいる。てんでばらばら。でも、書店という空間に、どこか惹かれて足を運ぶ。まさに出店が出ているときの神社です!
百々:はい! そこにいけば、これからの人生に役立つものに必ず出会える場所、それが書店です。そんな空間を大事にしたい。そして、当店はこれからもそういった場を提供していきたいと考えています。
梅田:なんだかやる気がでました! ぜひ、100年残る本を目指して、内容を突き詰めたコンテンツを創りたいと思います! ぜひまた相談させてください!
百々:はい! これは!というものがあれば、またお知らせください! 一緒に、良い物を届けましょう!

文・構成=山内貴範
編集=サンマーク出版 Sunmark Web編集部
◎前編はこちら

